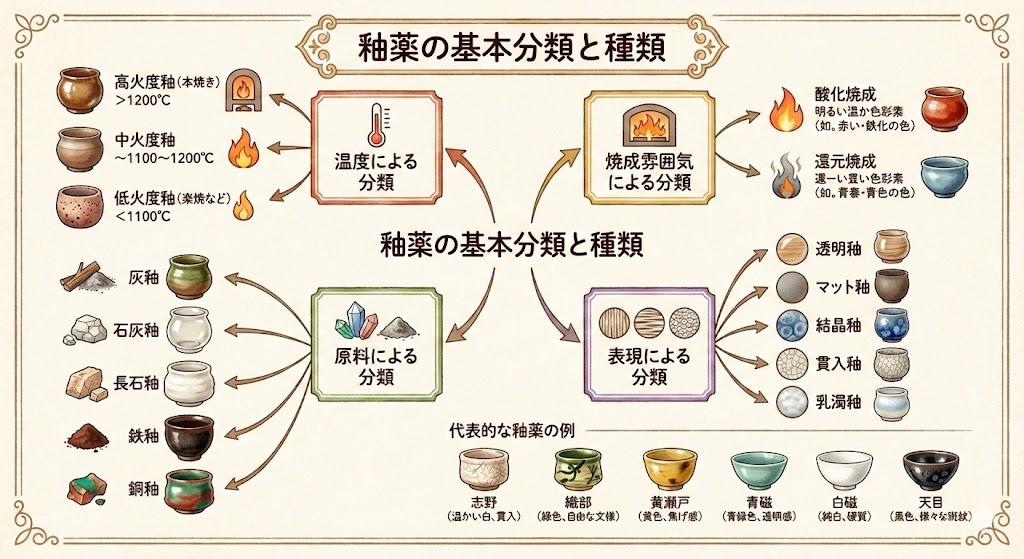土灰の釉薬としての特徴と使い方
土灰を水洗いせず使うと作品に黒い斑点が残ります
土灰とは何か?陶芸での基本的な位置づけ
土灰は田畑の土を焼いて作る灰のことで、陶芸では釉薬の重要な原料として使われています。日本では江戸時代から各地の窯元で使われてきた伝統的な素材です。
土灰の主成分は二酸化ケイ素(SiO2)が約60~70%、酸化アルミニウム(Al2O3)が約15~25%、その他酸化鉄や酸化カルシウムなどを含みます。この成分構成が釉薬として優れた性質を生み出すんですね。
植物灰(藁灰や木灰)と比較すると、土灰は融点が高く、釉薬として安定した性質を持つのが特徴です。藁灰が約1150℃で溶け始めるのに対し、土灰は1200℃以上の高温が必要です。
つまり高火度焼成に適した素材ということですね。
産地によって土の成分が異なるため、同じ「土灰」でも発色や質感が変わります。瀬戸地方の土灰は鉄分が多く茶色味を帯び、信楽の土灰は白っぽい仕上がりになる傾向があります。
土灰釉は単独でも使えますが、長石や石灰石などを配合することで、より幅広い表現が可能になります。配合比率を変えることで、透明度や発色、流れ具合を調整できるんです。
土灰釉の特徴的な発色と質感
土灰釉の最大の魅力は、焼成条件によって多彩な表情を見せることです。還元焼成では青白色や灰青色、酸化焼成では茶褐色や飴色に発色します。
還元焼成で得られる青白色は「青磁釉」に似た上品な色合いで、鉄分の含有量が0.5~2%程度の場合に美しく発色します。窯の中の酸素が不足する環境で、鉄が還元されて青みを帯びるんですね。
酸化焼成では鉄分が酸化鉄として残るため、黄土色から茶褐色の温かみのある色調になります。鉄分が3%以上含まれると、濃い飴色や黒褐色に近い発色も可能です。
これは使える表現ですね。
釉薬の厚さによっても表情が変わります。薄くかけると下地の素地が透けて見え、厚くかけると不透明で重厚な印象になります。厚さ0.3mm程度=爪の厚みくらいが標準的です。
表面の質感は、マットな梨地状から光沢のある艶肌まで調整できます。石灰石を多めに配合するとマットに、長石を増やすと光沢が出る傾向があります。
土灰だけの場合は半光沢が基本です。
窯変(ようへん)と呼ばれる予期しない発色も土灰釉の面白さです。窯の中での炎の流れや温度ムラによって、同じ釉薬でも一つ一つ異なる表情が生まれます。
土灰の作り方と水簸処理の重要性
土灰を作るには、まず田畑の土を集めて乾燥させます。使用する土は粘土質が少なく、砂や小石を多く含むものが適しています。
水田の土や畑の表土が一般的です。
乾燥した土を素焼き(800~900℃)程度で焼成します。この温度で有機物が燃焼し、土の構造が安定します。高温すぎると焼き締まって灰として使いにくくなるので注意が必要です。
焼成後の土を粉砕して灰にしますが、ここで重要なのが「水簸(すいひ)処理」です。水簸は灰を水に入れてかき混ぜ、沈殿の速度差で粒子を分離する作業のことですね。
水簸の手順は次の通りです。
- 灰を大量の水(灰の10倍程度)に入れる
- よくかき混ぜて一晩置く
- 上澄みを別容器に移す
- 沈殿物は捨てる
- この作業を3~5回繰り返す
水簸をすることで、砂や小石などの粗い粒子、溶けない有機物の残渣が除去されます。これをしないと、焼成時に黒い斑点や気泡が発生して作品の仕上がりが悪くなるんです。
水簸後の上澄みを沈殿させて乾燥させれば、純度の高い土灰の完成です。この状態の土灰は微細な粒子(10ミクロン以下=髪の毛の太さの10分の1以下)になっており、釉薬として均一に溶けやすくなります。
市販の土灰は水簸済みのものが多いですが、自家製の場合はこの工程を省略しないことが重要です。手間はかかりますが、作品のクオリティに直結する作業ですね。
土灰釉薬の配合レシピと調整方法
基本的な土灰釉の配合は、土灰単独または土灰に長石や石灰石を加える形が一般的です。
初心者向けの配合例を紹介します。
土灰100%の基本釉
- 土灰:100
これだけでも釉薬として機能しますが、溶けにくく透明度が低い傾向があります。
焼成温度は1250℃以上が目安です。
土灰長石釉(標準配合)
- 土灰:60~70
- 長石:30~40
長石を加えることで溶融温度が下がり、1200~1230℃で美しく溶けます。透明度も増して、下地の模様が活きる釉薬になります。
土灰石灰釉(マット調)
- 土灰:50~60
- 長石:20~30
- 石灰石:10~20
石灰石を加えるとマットな質感になり、柔らかい印象の仕上がりに。
発色も穏やかになる傾向があります。
配合の数字は重量比で、デジタル秤で正確に計量することが大切です。
誤差は±2%以内に抑えましょう。
つまり100gなら98~102gということですね。
釉薬の濃度調整も重要です。水と混ぜる際の目安は、釉薬粉末100に対して水50~70程度。指を入れて引き抜いたとき、指に0.5mm程度=クレジットカードの半分くらいの厚さの釉薬が付く濃度が適切です。
長期保存する場合は、腐敗防止のために防腐剤(ホウ酸など)を少量添加します。また、使用前には必ずよくかき混ぜて、沈殿した成分を均一にすることが必要です。
配合を変えて実験する際は、必ずテストピースで試し焼きをしてください。小さな素焼き片に釉薬をかけて焼成し、発色や質感を確認してから本番に使うのが原則です。
土灰釉の焼成温度と窯の雰囲気制御
土灰釉の焼成温度は1200~1280℃が標準的な範囲です。この温度帯で釉薬が溶けてガラス質になり、素地に密着します。
温度による違いを見ていきましょう。1200℃では釉薬が溶け始めたばかりで、やや不透明な仕上がりになります。1230~1250℃が最も安定して美しく仕上がる温度帯です。1280℃以上になると釉薬が流れすぎたり、素地が変形したりするリスクが出てきます。
焼成の雰囲気(酸化焼成か還元焼成か)で発色が大きく変わるのが土灰釉の特徴です。還元焼成では窯内の酸素を意図的に減らし、鉄分を還元させて青白色を引き出します。
還元焼成のタイミングは、温度が1000℃を超えたあたりから始めます。ダンパー(煙突の調整板)を少し閉じて、煙が出る状態を保ちながら昇温するんですね。
酸化焼成では十分な酸素を供給し、鉄分が酸化鉄として残るようにします。ダンパーを開け、炎が透明に見える状態を維持します。この場合は茶褐色や黄土色の発色が得られます。
温度測定には、ゼーゲルコーン(焼成用の温度指示材)やデジタル温度計を併用すると確実です。ゼーゲルコーンは目視で確認でき、デジタル温度計は連続的な温度変化を記録できます。どういうことでしょうか?
つまり、温度だけでなく温度の上がり方(昇温速度)も重要ということです。急激に温度を上げると釉薬が沸騰して気泡が残り、ゆっくり上げすぎると窯の燃料が無駄になります。1時間あたり100~150℃の昇温が目安ですね。
電気窯の場合は還元焼成ができないため、基本的に酸化焼成になります。
窯の種類によって得られる表現が変わることを理解しておきましょう。
冷却過程も大切です。最高温度到達後、1100℃くらいまでは自然冷却でOKですが、それ以下はゆっくり冷やすことで釉薬と素地の収縮率の違いによるヒビ(貫入)を防げます。
土灰釉を使った作品制作での注意点
土灰釉を作品に施釉する際は、素地の状態が重要です。素焼き後の素地は十分に乾燥させ、表面の汚れや油分を除去してから釉掛けします。
施釉方法には浸し掛け、流し掛け、吹き付けなどがありますが、土灰釉は比較的厚めにかけるのが基本です。浸し掛けの場合、3~5秒程度浸けるのが目安ですね。
素地の吸水性が高すぎると釉薬が厚くなりすぎ、逆に低すぎると薄くなります。素地の吸水率5~15%(素焼き800~900℃程度)が施釉しやすい範囲です。
釉薬の掛け合わせ(異なる釉薬を重ねる技法)を試す場合は、土灰釉を下層にすることが多いです。土灰釉の上に鉄釉や銅釉を重ねると、境界部分で独特の発色が生まれます。
高台(こうだい=器の底の輪)の部分には釉薬をかけないのが原則です。釉薬が溶けて棚板に付着するのを防ぐためですね。マスキングテープや撥水剤で保護してから施釉します。
焼成時の窯詰めでは、作品同士が触れないように間隔を空けます。土灰釉は流れやすいため、最低でも2cm程度=500円玉の直径くらいの間隔が必要です。
釉薬が流れて棚板に付着した場合、無理に剥がすと作品が割れることがあります。焼成前に高台の釉薬を削り取る、焼成後にグラインダーで削るなどの対処が必要です。
貫入(釉薬表面の細かいヒビ)は、土灰釉では比較的出やすい現象です。貫入を模様として活かすか、防ぎたいかで対応が変わります。防ぐには素地と釉薬の熱膨張率を合わせる配合調整が必要です。
食器として使う場合は、釉薬に鉛やカドミウムなどの有害物質が含まれていないことを確認してください。土灰釉自体には通常含まれませんが、配合する他の材料には注意が必要です。
安全性が条件です。
作品完成後は、使用前に一度煮沸することで貫入部分の汚れ吸着を防げます。米のとぎ汁で煮る「目止め」という処理も効果的です。