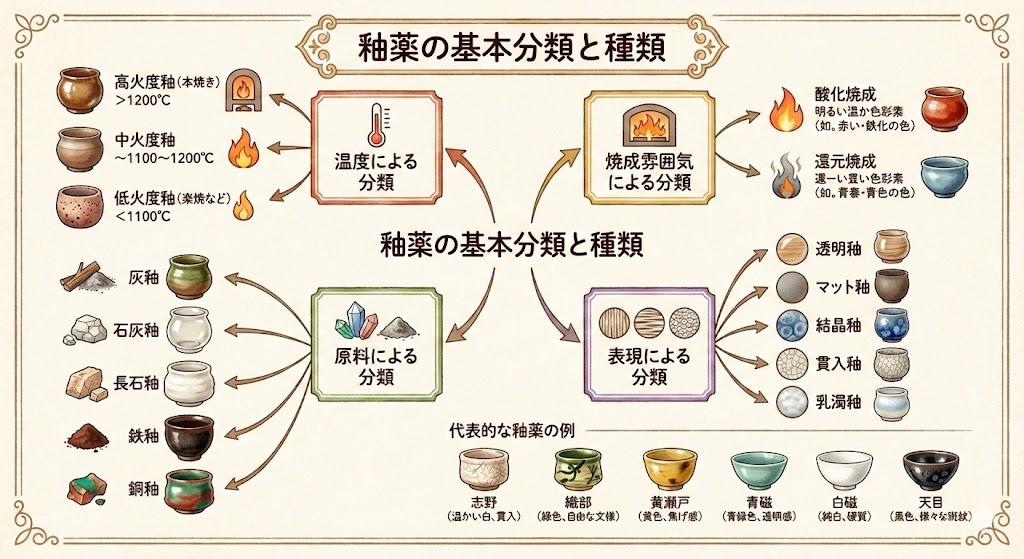灰釉の色と種類
同じ灰釉でも焼成温度が50℃違うだけで全く別の色になります。
灰釉の基本的な色の種類
灰釉は使用する植物灰の種類によって、大きく分けて5つの色系統に分類されます。藁灰を使った灰釉は青緑色から淡い緑色の発色が特徴で、日本では古くから「青磁釉」として珍重されてきました。木灰釉は茶褐色から黄褐色の温かみのある色合いを生み出します。
土灰釉は乳白色から灰白色の落ち着いた色調になります。竹灰を使うと透明感のある淡い黄色や緑がかった色が現れます。栗の木灰は深みのある茶色を発色することで知られています。
これらの色は原料灰に含まれる成分の違いから生まれます。特に鉄分、銅分、マンガン分などの金属酸化物の含有量が色を決める重要な要素です。
同じ種類の灰でも採取地域や季節によって成分が微妙に異なるため、全く同じ色を再現するのは困難です。
この不確実性が灰釉の魅力でもあります。
灰釉の色が変わる発色のメカニズム
灰釉の発色は焼成時の化学反応によって決まります。窯の中で1200℃以上の高温になると、釉薬中の金属酸化物が溶けて色を発します。
還元焼成では窯内の酸素が不足した状態になり、鉄分が青緑色の第一鉄(FeO)に変化します。これが青磁や青緑色の灰釉が生まれる仕組みです。一方、酸化焼成では酸素が豊富な環境で鉄分が茶褐色の第二鉄(Fe₂O₃)になります。
つまり還元焼成が基本です。
温度が50℃変わるだけで色が大きく変わる理由は、金属酸化物の反応温度が非常にシビアだからです。1200℃では淡い青緑だった釉薬が、1250℃では濃い緑に変わることもあります。
焼成時間も色に影響します。同じ温度でも長時間焼くと色が濃くなったり、逆に薄くなったりする現象が起きます。これは釉薬の成熟度と呼ばれる状態の違いです。
灰の種類別の発色特性と見分け方
藁灰釉は稲藁を燃やした灰を使います。カルシウム分が多く、鉄分が比較的少ないため、青緑色や淡い水色の発色が得られます。表面に細かい貫入(ひび模様)が入りやすいのも特徴です。
木灰釉は楢や樫などの広葉樹の灰を原料にします。鉄分とマンガン分を多く含むため、茶褐色から黄褐色の温かみのある色になります。表面に光沢があり、なめらかな質感が特徴です。
土灰釉は田んぼの土を焼いた灰を使用します。乳白色から灰白色の落ち着いた色調で、マットな質感になることが多いです。鉄分が少ないため、淡い色合いが基本となります。
竹灰釉は竹を燃やした灰から作ります。ケイ酸分が多く、透明感のある淡黄色や薄緑色を発色します。
ガラス質の美しい光沢が出やすい釉薬です。
各釉薬の見分け方は色だけでなく、表面の質感や貫入の入り方も重要な手がかりになります。
窯の種類と焼成方法による色の違い
電気窯で焼成すると安定した酸化焼成になるため、茶褐色系の発色が得られやすくなります。温度管理が正確にできるので、同じ色を再現しやすいのが利点です。
ただし還元焼成特有の青緑色は出せません。
ガス窯では還元焼成が可能なため、青磁のような青緑色の灰釉を作ることができます。窯内の酸素量を調整することで、還元と酸化の中間的な色合いも表現できます。
薪窯は最も伝統的な焼成方法です。窯内の場所によって温度や雰囲気が異なるため、同じ釉薬でも作品ごとに色が変わります。
この予測不可能性が薪窯焼成の魅力です。
焼成温度の目安は以下の通りです。
- 1200~1230℃:淡い色合い、透明感のある発色
- 1230~1260℃:標準的な発色、釉薬が十分に溶ける
- 1260~1300℃:濃い色合い、釉薬が流れやすい
温度が高すぎると釉薬が流れ落ちて作品の形が崩れることがあります。低すぎると釉薬が十分に溶けず、ざらついた表面になります。
どの窯を使うかで作品の仕上がりが大きく変わるということですね。
灰釉の色を安定させる調合と管理のコツ
灰釉の色を安定させるには、まず原料灰の管理が重要です。灰は湿気を吸いやすく、保管状態で成分が変化します。密閉容器に乾燥剤と一緒に保管し、使用前に必ず篩にかけて粒度を揃えます。
基本的な調合比率は灰60~70%、長石20~30%、石灰石5~10%が目安です。この比率を基準に、発色を調整するために鉄分や銅分を微量添加します。鉄分を1~3%加えると茶褐色が強くなり、銅分を0.5~2%加えると青緑色が強くなります。
調合時は必ずテストピースを作って試し焼きをすることが基本です。本焼きと同じ温度・雰囲気で焼成し、色を確認してから本番の作品に使います。
記録も重要な管理項目です。使用した灰の種類、調合比率、焼成温度、焼成時間、窯の雰囲気を必ずメモしておきます。同じ色を再現したい場合に、この記録が頼りになります。
季節による変化にも注意が必要です。春に採取した藁灰と秋に採取した藁灰では成分が異なることがあります。安定した発色を求めるなら、同じ時期に採取した灰をまとめて保管し、長期間使用するのがコツです。
色の再現性を高めたい場合は、市販の調合済み灰釉を使うのも一つの方法です。成分が安定しているため、毎回同じ色が出やすくなります。
つまり記録と管理が安定した発色の鍵です。