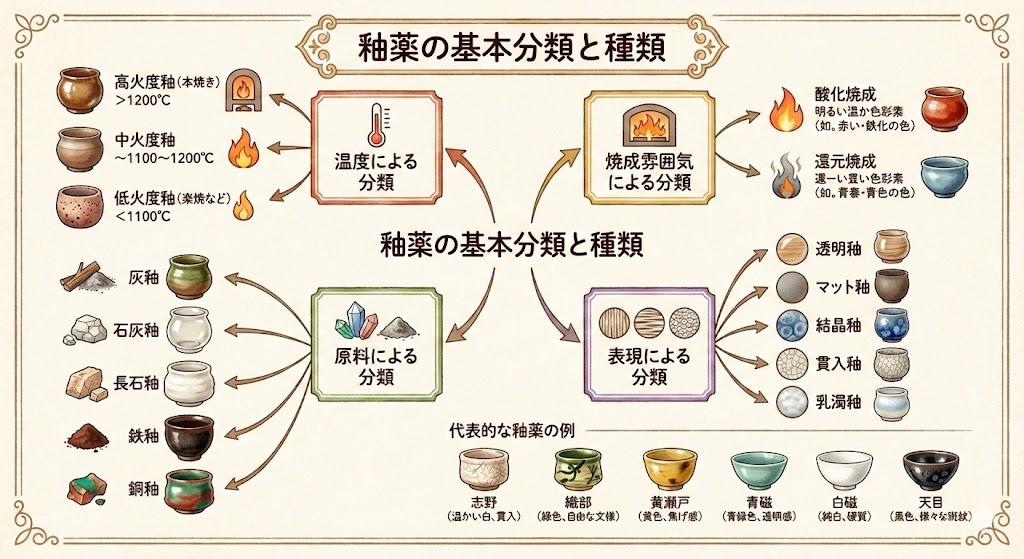分焔式 構造 メリット
分焔柱なしで焼くと作品に100℃以上の温度差がつきます。
分焔式の窯とは何か基本構造を理解する
分焔式とは、窯の燃焼室と焼成室の間に「分焔柱(ぶんえんちゅう)」と呼ばれる柱を設置し、炎を左右に均等に分散させる窯の構造を指します。焚口から送り込まれた火焔は分焔柱にぶつかり、二手に分かれて焼成室の両側へ広がります。
参考)窯の発展の歴史 04|みずなみ焼・美濃焼陶器製作の山喜製陶株…
炎は何もなければ煙突の方向へ直進し、左右の壁際に置いた作品がうまく焼けない問題が発生します。分焔柱が炎を左右に振り分けることで、焼成室全体に熱量が行きわたる仕組みです。
この構造は天井を支える役割も兼ねており、窯の強度維持にも貢献しています。分焔柱は日本独自の技術として愛知県の猿投窯で発明され、中世窯への移行期を象徴する重要な発明となりました。
参考)やきものPLAZA
発明後は静岡県の湖西や浜北の窯にも採用され、全国へと広がっていきます。猿投窯では分焔柱がない古いタイプと、発明後の新しいタイプの両方が発掘されているため、技術発展の過程を確認できる貴重な遺跡となっています。
参考)http://museum.starfree.jp/201_kama/30100main.html
分焔柱が温度ムラを防ぐ仕組み
窯内の温度差は作品の焼き上がりに直接影響する重要な問題です。分焔柱を使用すると、窯内前後・上下ともに焼成温度の差を100℃以下に抑えることができます。
参考)https://www.pref.aichi.jp/touji/about-aito/pdf/2012aitou_03_tamura.pdf
これは決して小さな数字ではありません。温度差が100℃を超えると、同じ窯の中でも焼き過ぎや焼き不足の作品が混在し、歩留まりが大幅に低下します。分焔柱による温度管理がなければ、1回の焼成で使えない作品が大量に出るリスクがあるということです。
実際の焼成では、炉内温度を低く抑える炙り段階では分焔柱からかなり離れた位置で焚火を行い、種火部分を500℃程度に保ちます。このように分焔柱の位置を基準に焚火の場所を調整することで、細かな温度コントロールが可能になります。
参考)https://senshu-u.repo.nii.ac.jp/record/2194/files/1051_0092_17.pdf
香久山古窯では長さ7.9メートル、幅2メートルの窯内に分焔柱を残す貴重な遺構が保存されており、この柱が温度調整の要として機能していたことが確認できます。窯内の温度ムラは作品の品質に直結するため、分焔柱の設置は陶工にとって必須の技術だったといえます。
参考)2021年6月13日 香久山古窯から学ぶやきもののルーツ/日…
分焔式窯のメリットと燃料効率
分焔式を採用した連房式登窯は、従来の穴窯や窖窯と比較して熱効率が大幅に向上したことが最大のメリットです。地上に窯を設置する構造のため、地下や半地下の窖窯が抱えていた湿気による温度低下の問題を克服しました。
結果として燃料消費を抑えながら高温を維持できるようになり、コスト削減と生産性向上を同時に実現します。従来の窯では湿気の影響で燃料を大量に投入しても思うように温度が上がらず、陶工たちは常に燃料確保に悩まされていました。
複数の焼成室で一度に多数の作品を焼成できるため、大量生産能力も飛躍的に向上しました。単室の穴窯や大窯と比べて生産量が増加し、商業的な陶器生産が可能になったのです。
下の部屋の熱が上の部屋へ効率的に伝達される廃熱再利用システムにより、エネルギー効率が飛躍的に改善されました。一番窯を焼き上げる頃には二番窯が充分に熱せられており、かなり短時間で焼き上げることが可能です。
参考)http://www.naraokayaki.com/climbingkiln.html
窯の発展の歴史を詳しく知りたい方は、美濃焼の歴史を紹介するこちらのページが参考になります。
分焔式窯の歴史と猿投窯での発明
分焔柱の技術は日本独特であり、愛知県の猿投窯で開発されました。猿投窯は古墳時代から鎌倉時代にかけて愛知県で稼働していた古窯群で、1,000基を超える規模を誇ります。
参考)猿投窯とは
その古窯群は名古屋市の東部から瀬戸市南端、豊田市西部から刈谷市・大府市まで約20km四方の地域に分布していました。須恵器の生産地として約900年という長期間稼働し続けた点も特筆すべき特徴です。
平安時代初期には分焔柱発明以前の半地下スサ入り粘土天井の窖窯で灰釉陶器の高級品を焼いていました。しかし温度管理の難しさや燃料効率の悪さから、技術革新が求められていたのです。
分焔柱発明後の窯は焼けしまっていて遺存することが多いため、窯跡を見ると一目で時代がわかります。考古学的にも重要な指標となっており、中世窯への移行期を示す決定的な証拠となっています。
猿投窯で生まれた技術は瀬戸・美濃地域へ伝わり、やがて全国の窯業地に広がって日本の陶磁器生産を支える基盤技術となりました。
分焔式窯における実際の焼成作業
分焔式の登り窯での焼成は、大口(燃焼室)から始まり、攻め焚きの段階では小口(各部屋の横に作られた薪投入口)から薪を投げ入れます。一度に投げ入れる薪の量やタイミングによって窯の中の温度が大きく左右されるため、最も集中力が要る段階です。
燃料には主に赤松が使われており、油を多く含んでいるため炎が強く長く伸びるという特性があります。備前焼では1週間から2週間ほど赤松の薪を燃料にして登り窯で焼成する場合が多く、膨大な量の薪が必要です。
つまり長期間の焼成には相当な準備が必須ということです。
ただし近年では登り窯の燃料となる薪(松の木)の確保が難しくなってきたこと、登り窯が排出する煙、窯焚きにおける労力の問題から、登り窯の数や焼成回数は急速に減少しています。自然環境を守るという観点からも、薪の大量消費は課題となっているのです。
手軽で比較的安定焼成のできる電気窯やガス窯が普及したことも、登り窯減少の一因です。しかし分焔式窯で焼かれた作品には、現代の窯では出せない独特の表情があり、今でも多くの陶芸家が薪窯での焼成にこだわり続けています。
現代でも分焔式の技術を理解することは、陶芸における温度管理や炎の動きを学ぶ上で重要な知識となります。
日本のやきものと窯の詳細については、日本陶磁協会のサイトで技術的な解説が読めます。