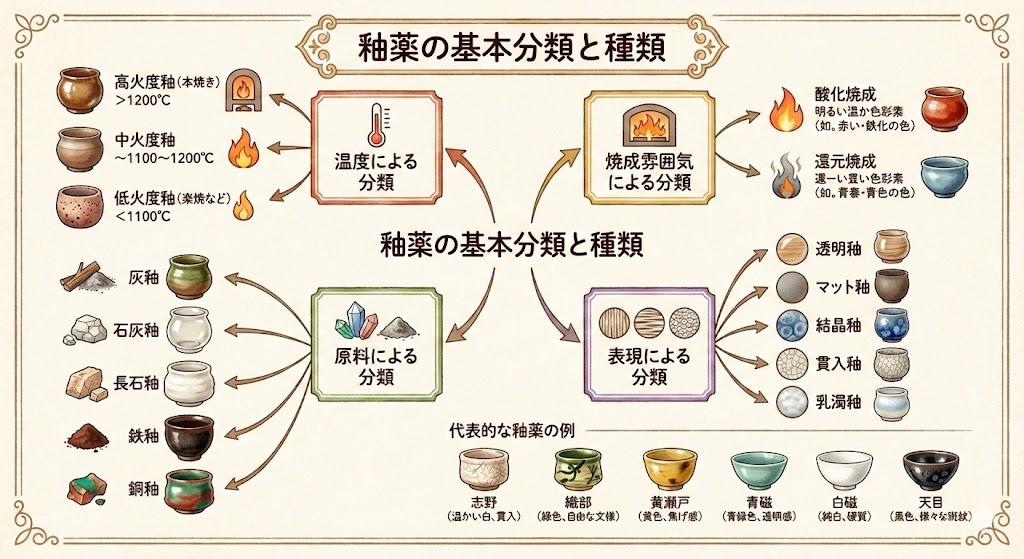釉飛び原因と対策
釉薬を厚く塗れば塗るほど釉飛びは起こりにくくなる。
釉飛びが起こる主な原因とメカニズム
釉飛びは、焼成後の陶器表面から釉薬が剥がれ落ちる現象です。この現象の背後には、素地と釉薬の物理的な性質の違いが関係しています。
最も一般的な原因は、素地と釉薬の熱膨張率の不一致です。焼成時に高温まで加熱された陶器は、冷却過程で収縮します。このとき、素地と釉薬の収縮率が異なると、釉薬層に引っ張り応力が発生します。この応力が釉薬の接着力を上回ると、釉薬が素地から剥離してしまうのです。
具体的には、釉薬の膨張率が素地より0.5~1.0×10⁻⁶/℃以上大きい場合、釉飛びのリスクが高まります。これは、1000℃から常温まで冷却する過程で、釉薬が素地より約0.05~0.1%多く収縮することを意味します。わずか1mm程度の厚さの釉薬層でも、この差が剥離を引き起こすのです。
施釉の厚さも重要な要因です。釉薬を厚く塗りすぎると、釉薬層自体の重さと内部応力が増大し、素地との接着面に過度な負担がかかります。一般的に、釉薬の適切な厚さは0.5~1mm程度とされています。
これより厚いと釉飛びのリスクが高まります。
つまり適切な厚さ管理が必要です。
焼成温度の管理不足も見逃せません。釉薬が十分に溶融しない低温焼成では、素地との結合が不十分になります。逆に高温すぎると、釉薬が過度に流動し、冷却時の収縮が大きくなります。各釉薬には最適焼成温度があり、それを外れると釉飛びが発生しやすくなるのです。
素地の状態も影響します。素地に油分や汚れが付着していると、釉薬の密着性が低下します。また、素焼きの温度が低すぎて素地の吸水性が高いままだと、施釉時に水分を過剰に吸収し、釉薬層が不均一になります。
これも釉飛びの原因です。
釉飛びを防ぐための釉薬選びと素地との相性
釉飛びを防ぐには、素地と釉薬の相性を見極めることが最優先です。相性の良い組み合わせを選ぶことで、釉飛びのリスクを大幅に減らせます。
まず確認すべきは、素地の種類です。磁器用の素地、陶器用の素地、炻器用の素地では、それぞれ異なる熱膨張特性を持ちます。磁器は膨張率が低く、陶器は比較的高い傾向があります。使用する素地に合わせて、適合する釉薬を選ぶことが基本です。
市販の釉薬には、適合する素地の種類や焼成温度範囲が明記されています。例えば「磁器・半磁器用」「陶器用」「1230℃~1250℃」といった表示です。
これらの情報を必ず確認しましょう。
相性を確認する最も確実な方法は、テストピースでの試し焼きです。本番の作品を作る前に、小さなテストピースに釉薬を施し、実際の焼成条件で焼いてみます。冷却後、釉薬の剥がれや亀裂がないか、指で軽く叩いて釉薬が浮いていないか確認します。
これが基本です。
複数の釉薬を組み合わせる場合は、さらに注意が必要です。下釉と上釉の膨張率の違いによって、層間で剥離が起こることがあります。重ね掛けする釉薬の相性も、必ずテストで確認してください。
釉薬メーカーが提供する技術資料も有用です。多くのメーカーは、釉薬の熱膨張係数や推奨される素地との組み合わせをデータシートで公開しています。特に新しい釉薬を試す際は、これらの資料を入手して確認すると安心です。
日本セラミックス協会の技術資料には、釉薬と素地の相性に関する詳細な情報が掲載されています。
経験を重ねるうちに、自分がよく使う素地と相性の良い釉薬のリストができてきます。このリストを記録として残しておくと、今後の作品作りで失敗を減らせます。焼成温度、施釉方法、結果を含めて記録することをおすすめします。
釉飛びを起こさない施釉の厚さと技法
施釉の厚さは釉飛び防止の要です。適切な厚さを守ることで、美しく耐久性のある釉薬層を形成できます。
標準的な釉薬の厚さは0.5~1mmです。これは、1円玉の厚さ(1.5mm)より薄く、名刺の厚さ(0.2mm)の2.5~5倍程度です。この範囲を守ることで、釉薬の密着性と表面の美しさを両立できます。
厚すぎる施釉は最も避けるべきミスです。1.5mm以上の厚さになると、釉薬層の重さと収縮応力が増大し、釉飛びのリスクが急激に高まります。特に縦面や曲面では、重力の影響で釉薬が流れやすくなり、さらに問題が悪化します。
薄すぎても問題です。0.3mm以下の薄い施釉では、釉薬が十分に溶融しても素地の質感が透けて見え、期待した発色が得られません。
また、釉薬層が薄いと保護機能も低下します。
施釉方法によって厚さの調整方法が異なります。
浸し掛けの場合
- 浸す時間は2~5秒程度
- 素地の吸水性に応じて調整
- 2度掛けする場合は各1~3秒
刷毛塗りの場合
- 2~3回の薄塗り重ねが基本
- 1回塗りで厚くしない
- 刷毛跡を均一に整える
吹き付けの場合
- 距離20~30cmを保つ
- 複数回の薄い吹き付け
- 均一な厚さを意識
厚さを確認する簡単な方法があります。施釉直後、爪楊枝や針で釉薬層に垂直に刺し、素地に達したところで止めます。引き抜いた後、濡れた部分の長さを測れば、おおよその厚さがわかります。
どうなるんでしょう?
縁や角など、釉薬が薄くなりやすい部分には注意が必要です。これらの部分は意識的に厚めに施釉するか、施釉後に補修します。ただし、厚くしすぎると逆に釉薬が流れ落ちるので、バランスが重要です。
釉飛びを防ぐ焼成温度と冷却の管理方法
焼成温度と冷却過程の管理は、釉飛び防止において技術的に最も重要な要素です。適切な温度管理により、素地と釉薬の最適な結合を実現できます。
各釉薬には最適焼成温度範囲があります。例えば、一般的な陶器用釉薬は1200℃~1250℃、磁器用釉薬は1250℃~1300℃が標準です。この範囲から外れると、釉薬が十分に溶融しなかったり、過度に流動したりして、釉飛びのリスクが高まります。
温度計の精度も確認が必要です。窯の温度計が実際の温度と±20℃以上ずれていることは珍しくありません。定期的に校正するか、信頼できる温度計で確認することをおすすめします。ゼーゲルコーンを併用すると、より正確な焼成管理ができます。
上昇速度も影響します。急激な昇温は素地内の水分や有機物の放出を妨げ、釉薬層と素地の間にガスが溜まります。
これが釉飛びの原因になることがあります。
600℃までは1時間あたり100℃程度のゆっくりとした昇温が安全です。
つまりゆっくり加熱が鉄則です。
最高温度での保持時間も重要です。
適切な保持時間は10~30分程度です。
これにより、釉薬が均一に溶融し、素地との結合が強固になります。保持時間が短すぎると釉薬の溶融が不十分で、長すぎると釉薬が過度に流動します。
冷却過程は特に注意が必要です。
急冷は釉飛びの最大の原因の一つです。
特に600℃から400℃の範囲では、1時間あたり50℃以下のゆっくりとした冷却が推奨されます。この温度帯で素地と釉薬の収縮率の違いが最も顕著に現れるためです。
窯の開け方にも配慮が必要です。200℃以下になるまで窯を開けないのが基本です。それより高温で開けると、外気との急激な温度差で釉薬に亀裂が入ったり、剥離したりします。
触って熱くない温度まで待ちましょう。
電気窯を使用する場合、プログラム機能を活用できます。昇温速度、最高温度、保持時間、冷却速度を細かく設定できるため、釉飛びを防ぐ最適な焼成カーブを作成できます。一度成功したプログラムは保存し、同じ条件を再現しましょう。
日本窯業協会の焼成技術ガイドでは、釉薬の種類別の最適焼成条件が詳しく解説されています。
記録を残すことも大切です。焼成ごとに、使用した釉薬、素地、温度カーブ、結果を記録します。釉飛びが発生した場合、この記録を分析することで原因を特定し、次回の改善につなげられます。
釉飛びが発生した作品の修復と再利用法
釉飛びが発生してしまった作品でも、適切な処置により修復や再利用が可能な場合があります。状況に応じた対処法を知っておくと、作品を救える可能性が広がります。
軽度の釉飛び(直径5mm以下の小さな剥離が数カ所)の場合、研磨処理で目立たなくすることができます。耐水ペーパー(400番~1000番)を使い、剥離部分の縁を滑らかに削ります。その後、2000番以上の細かいペーパーで磨くと、剥離跡が目立ちにくくなります。
ただし、この方法は食器など実用品には不向きです。研磨した部分は釉薬の保護がなく、汚れが染み込みやすくなります。鑑賞用の作品や、装飾部分の軽度な釉飛びに限定して使いましょう。
中度の釉飛び(直径1cm以上の剥離や、複数箇所の釉飛び)では、再施釉と再焼成が有効です。剥離した部分の素地をサンドペーパーできれいに研磨し、埃や油分を除去します。その後、同じ釉薬を該当部分に塗布し、本焼成よりやや低めの温度(50℃程度低い)で焼成します。
これで修復できます。
再焼成時の注意点があります。初回焼成で釉薬が溶融している周辺部分は、再焼成で過度に流動する可能性があります。そのため、再施釉する範囲は最小限に抑え、周囲との境界をぼかすように塗布すると、境目が目立ちにくくなります。
重度の釉飛び(広範囲の剥離や、構造的な問題を伴う釉飛び)の場合、全体の釉薬を剥がして再施釉する方法もあります。剥離剤を使うか、機械的に削り取り、素地を露出させます。
その後、新たに施釉して焼成し直します。
ただし、この方法は素地に負担をかけます。特に薄手の作品や繊細な造形の作品では、破損のリスクがあります。実施前に、作品の価値と手間を天秤にかけて判断してください。
修復が困難な作品は、別の用途に転用できます。
転用例
- 花器として使う(内側の釉飛びは水に影響しない)
- 装飾品として飾る(実用しない)
- ガーデニング用の鉢として使う
- モザイクタイルの素材にする
失敗作から学ぶことも重要です。釉飛びが発生した作品を保管し、原因を分析します。施釉の厚さ、焼成条件、素地との相性などを記録し、次回の制作に活かします。
失敗は最良の教師です。
釉飛び予防のための日常的なチェックポイント
釉飛びを防ぐには、制作工程全体での継続的な注意が必要です。日常的なチェックポイントを習慣化することで、トラブルを未然に防げます。
素地の準備段階でのチェックが第一歩です。素焼き前に素地表面を確認し、油分や埃が付着していないか確認します。
触って手に何も付かない状態が理想です。
汚れがある場合は、湿らせた布で拭き取ります。
素焼きの焼成温度も記録します。一般的に800℃~900℃が適切ですが、使用する粘土によって最適温度は異なります。素焼き温度が低すぎると吸水性が高すぎ、高すぎると吸水性が低すぎて、どちらも施釉に悪影響を与えます。
施釉前には素地の吸水性をチェックします。素地に水を数滴垂らし、吸収速度を観察します。
5~10秒で吸収される程度が適切です。
瞬時に吸収される場合は素焼き温度が低すぎ、なかなか吸収されない場合は高すぎる可能性があります。
厳しいところですね。
釉薬の管理も重要です。使用前に釉薬をよく攪拌し、沈殿物がないか確認します。長期保管した釉薬は、成分が分離していることがあります。攪拌後、比重計で比重を測定し、記録と比較すると、釉薬の状態を客観的に把握できます。
施釉後のチェックも欠かせません。釉薬が乾燥したら、表面を指で軽く触り、厚さが均一か確認します。厚すぎる部分はスポンジで軽く拭き取り、薄すぎる部分は追加で施釉します。
窯詰めの際には、作品同士の間隔を十分に取ります。
最低でも3cm以上の間隔が必要です。
近すぎると、焼成中に釉薬が流れて作品同士がくっついたり、熱の循環が悪くなって焼きムラの原因になります。
焼成記録を毎回つけることも習慣にしましょう。
以下の項目を記録します。
記録項目
- 使用した素地と釉薬の種類
- 施釉の厚さと方法
- 焼成温度カーブ
- 最高温度と保持時間
- 冷却時間
- 結果(成功/失敗の詳細)
定期的な窯のメンテナンスも忘れずに。温度センサーの校正、ヒーターの劣化チェック、窯内の清掃を行います。特に温度センサーは、使用を重ねるうちに誤差が大きくなります。
年1回程度の校正が推奨されます。
コミュニティでの情報交換も有効です。陶芸教室や陶芸家の集まりで、釉飛びの経験や対策を共有すると、新しい知見が得られます。同じ素地や釉薬を使っている人の経験は、特に参考になります。