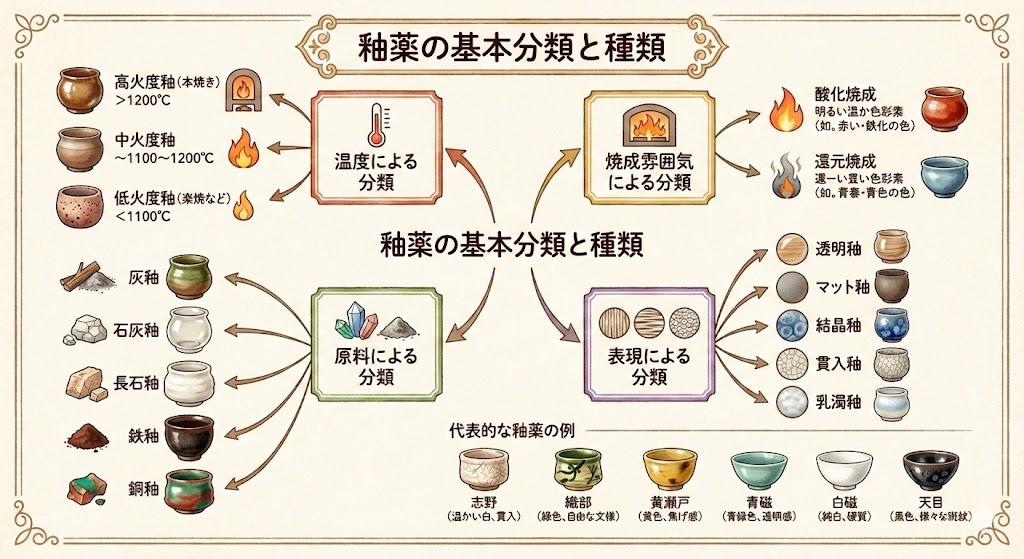単室登窯とは
単室登窯は長さ30m超えても均一に焼けません。
単室登窯の基本的な構造
単室登窯は、斜面を利用して築かれた単一の焼成室を持つ窯のことです。上から見ると竹を割ったような長方形の形状をしているため、「割竹式(わりたけしき)」とも呼ばれます。
参考)蛇窯(鉄砲窯、龍窯)
一般的な連房式登窯が複数の焼成室を間仕切りで区切っているのに対し、単室登窯は仕切りのない一つの長い空間で構成されています。炎は焚口から煙突まで一定の傾斜を駆け上がっていく仕組みです。
参考)http://www.arc.ritsumei.ac.jp/archive01/jimu/publications/kidachi/kyoyaki/11/kidachi_kyoyaki-11.pdf
この構造は連房式登窯が普及する以前の古い形式ですが、特定の地域や用途では現代まで使われ続けてきました。
つまり歴史的な窯形式です。
薩摩焼の古窯である堂平窯(どびらがま)跡は、長さ30.5m、幅1.2m、傾斜17度の円筒形の単室登窯として知られています。この長さで単室構造だと、炎はまっすぐ駆け上がり、分煙柱があっても窯の中央部分しか作品が焼けない構造的な課題がありました。
参考)登窯(登り窯)
単室登窯の焼成上の特徴と課題
単室登窯の最大の特徴は、炎の流れが一方向に限定されることです。横幅がある単室登窯では、内部の壁際を炎が通りにくく、中央以外はうまく焼けないおそれがあります。
火が一方に偏るなど、横幅が広ければ広いほど均一に焼けないリスクが高まります。そこで窯の側面に薪を入れる穴を複数設けることで、この問題に対処しています。
側面からの薪投入が基本です。
増穂登り窯の例では、幅3.5m、入り口から煙突まで6m、高さ2mの大型単室窯に、10カ所以上の大小焚口が設けられました。正面と左右各2カ所の通常焚き口に加え、天上部分にも左右各3カ所、合計6カ所の焚き口を付けることで、窯内全体に熱を行き渡らせる設計となっています。
参考)池田満寿夫と増穂登り窯 – 増穂登り窯 公式ウ…
このように複数の焚き口を駆使しなければ、単室登窯で均一な焼成を実現することは困難です。温度管理と薪の投入タイミングには高度な技術と経験が求められます。
単室登窯の歴史的背景
単室登窯は中国の青磁生産で使われた龍窯(りゅうがま)をルーツとしています。龍窯は斜面を利用した単室の窯で、いわゆる広義の登り窯の一形態です。
日本では、薩摩焼の陶工が琉球に製陶技術を伝えた際、単室登窯が導入されました。苗代川から伝わった窯構造は、その後の琉球陶器の基本技術として定着したと考えられています。
参考)http://www.edu.city.naha.okinawa.jp/tsuboya/kiyou/kiyou19%20watanabe.pdf
琉球陶器の技術の基礎です。
やがて単房(単室)であった穴窯に間仕切りを設け、間仕切りの下に狭間穴を明けた割竹式登り窯が出現しました。これが現在も使われている連房式登窯の祖型となっています。
つまり単室登窯は、穴窯から連房式登窯へと進化する過程における重要な中間形態だったのです。効率性を追求した結果、複数の焼成室を持つ連房式へと発展していきましたが、単室登窯の技術がその基礎となりました。
単室登窯を平地に築く工夫
通常、登窯は斜面を利用して築かれますが、平地に単室登窯を築く試みも行われてきました。平地での築窯には炎の引きと窯内の蓄熱という課題があります。
増穂登り窯では、高さ6mの煙突を設置し、本窯と煙突との中間に1立方mの火袋部屋を作ることで、この問題を解決しました。火袋部屋によって炎の引きと蓄熱が改善され、平地でも十分な焼成が可能になったのです。
煙突の高さが鍵になります。
外壁には耐火セメントも使用して強固に築窯し、安定した焼成環境を実現しています。焚き口も正面を大きく開放できる設計とし、人間2人が立ったまま同時に入れるサイズとすることで、窯詰めと薪投入の作業性を向上させました。
こうした工夫により、斜面がない場所でも単室登窯を運用できるようになりました。ただし、煙突の建設コストや火袋部屋の設計など、平地築窯には追加の投資と専門知識が必要です。
単室登窯と連房式登窯の違い
単室登窯と連房式登窯の最大の違いは、焼成室の数です。単室登窯は一つの長い空間で構成されるのに対し、連房式登窯は複数の部屋(房)が連なっています。
参考)空気を焼く陶磁器/穴窯・登窯・唐津焼・美濃焼・加藤景延|美術…
連房式登窯が効率的とされる理由は、各房を段階的に焼成できる点にあります。下の房が十分に焼けたら焚き口を塞ぎ、次の房の焚き口から薪を投じることで、順次焼成を進めていきます。
効率的な陶磁器生産が可能です。
一方、単室登窯は全体を一度に焼成するため、温度管理が複雑になります。しかし、独特の炎の流れによって生まれる焼成効果を求めて、現代でも一部の陶芸家が単室登窯を使用しています。
歴史的には連房式登窯が単室登窯より後世に完成されたもので、より効率的に陶磁器の焼成ができる窯として普及しました。それでも単室登窯には、連房式にはない独自の表現可能性があるため、作家性を重視する陶芸家にとっては魅力的な選択肢となっています。
単室登窯での焼成プロセス
単室登窯での焼成は、火入れから完了まで24時間以上を要する長時間作業です。火入れから12時間後には窯内の温度が1000度を超え、このあたりから薪を投じるタイミングが早くなっていきます。
薪を投じるごとに窯内の酸素が少なくなり、不完全燃焼の状態が生じます。
その際、煙突からは黒い煙が立ちます。
煙の色で状態を判断します。
火入れから12〜24時間後は、2人が窯の正面に構え、温度が下がらないようタイミングを見ながら同時に薪を投じる作業を繰り返します。多く入れすぎると窯内の酸素が不足して温度が急に下がるため、数分に1回のペースでの投入が必要です。
最終的に1300度近い温度で十分に焼けたところで、焚き口を煉瓦で塞ぎ、隙間から空気が入らないようモルタルを塗って仕上げます。この緻密な温度管理と薪投入のタイミング調整が、単室登窯焼成の難しさであり、同時に陶芸家の技量が問われる部分でもあります。
焼成中は常に窯の様子を観察し、色見穴から内部の状態を確認しながら作業を進める必要があります。この経験と勘に基づく判断が、作品の仕上がりを左右するのです。