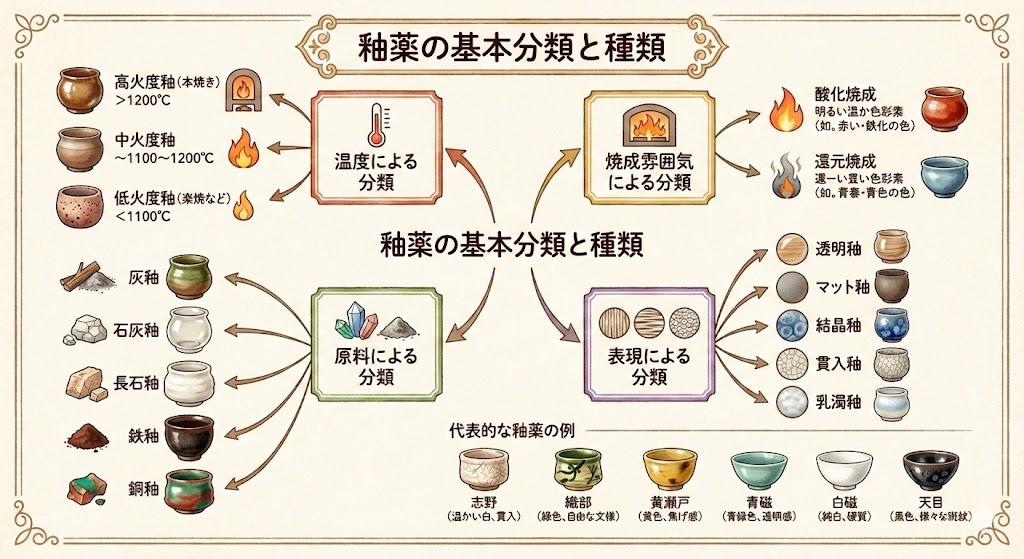碁笥底とは|陶芸における底づくり
碁笥底は釉薬を付けたまま焼くと棚板と作品がくっついてしまいます。
碁笥底とは陶芸用語の基本定義
碁笥底(ごけぞこ)とは、陶芸における底づくりの技法の一つで、高台を作らずに底面を碁石入れの底のような形状に仕上げる方法です。碁笥とは囲碁で使う碁石を入れる丸い容器のことを指します。
参考)碁笥底 ごげぞこ
この技法の最大の特徴は、底の中心部が凹んでいて、その縁が多少上がっている点にあります。いわゆる上げ底風の構造ですが、角がなく滑らかな曲線で構成されているのが特徴です。
参考)http://blog.livedoor.jp/toraku/archives/20836710.html
土瓶や急須などに最も多く見られる底づくりであり、実用的な器から茶道具まで幅広く採用されています。普通の高台より品格が高いとも言われる技法です。つまり機能性と美しさを兼ね備えた技法ということですね。
碁笥底の構造と形状の特徴
碁笥底の構造を正確に理解するには、中心部と縁の関係を把握することが重要です。単に中心部だけを凹ませただけではなく、その縁は多少上がっている形状になります。この微妙な立ち上がりが、碁笥底の品格を生み出す要素です。
底面には通常、3点のトチ(耐火粘土の支持材)の痕が残ります。これは焼成時に作品を支えるために使用されるもので、碁笥底特有の焼成方法を示す証拠でもあります。トチ痕は直径数ミリ程度の小さな跡ですが、作品の真贋や時代を見極める手がかりにもなります。
参考)https://ameblo.jp/waki-japan/entry-12169551419.html
高台がないため、のっぺりとした印象を与える底面ですが、この形状こそが碁笥底の本質です。中心の凹みの深さや縁の立ち上がり角度によって、作品全体の印象が大きく変わります。黄瀬戸茶碗などの名品では、この微妙なバランスが完璧に計算されています。
参考)碁笥(ごけ)底・Gokezoko – 茶の湯 i…
碁笥底が使われる陶芸作品の種類
黄瀬戸茶碗は碁笥底の代表的な作品として知られています。茶道の世界では、この底づくりが品格の高さを示す要素として評価されてきました。黄瀬戸は桃山時代に美濃地方で焼かれた黄色い釉薬の陶器で、碁笥底はその特徴的な技法の一つです。
土瓶と急須は、実用的な器として碁笥底が最も多く採用されている分野です。底面が広く安定しているため、日常使いに適しており、釉薬を底まで施せるという利点もあります。市販されている急須の多くが、実は碁笥底の構造を採用しています。
考古学の分野でも、碁笥底の杯(つき)などが発掘されています。直径4cmほどの小さな杯に碁笥底が用いられていた例もあり、古くから様々なサイズの器に応用されてきた技法であることが分かります。
これは使えそうです。
碁笥底の制作で注意すべき釉薬の扱い
碁笥底の高台には釉薬をつけたままにして焼く特徴がありますが、これには技術的な課題が伴います。通常、高台に釉薬が付いていると焼成時に溶けて作品と棚板がくっついてしまうためです。この問題を解決するために、トチという耐火粘土の支持材を使用します。
トチは通常3点を底面に配置し、作品を棚板から浮かせた状態で焼成します。この方法により、釉薬が溶けても棚板と直接接触しないため、くっつきを防げます。ただしトチ痕が残るというデメリットもあります。
釉薬を底まで施せることで、作品全体に統一感が生まれ美しい仕上がりになります。しかし焼成温度や釉薬の流れ具合を正確に計算しないと、トチ部分から釉薬が流れ出して失敗する可能性もあります。
温度管理が条件です。
碁笥底制作における独自の成形のコツ
碁笥底を美しく仕上げるには、中心部の凹みと縁の立ち上がりのバランスが鍵を握ります。ろくろで成形する場合、底面を削り出す際に一気に凹ませるのではなく、少しずつ形を整えていく必要があります。削りすぎると強度が落ちて、焼成時に変形や割れのリスクが高まります。
縁の立ち上がり角度は5~10度程度が理想的です。これは分度器で測った角度ではなく、見た目で「わずかに立ち上がっている」と感じる程度の微妙なラインです。急すぎると不自然に見え、緩すぎると碁笥底の特徴が失われます。
手びねりで制作する場合は、型を使って底面の形状を安定させる方法も有効です。陶芸教室では型を使った碁笥底の練習から始めると、理想的な形状を体で覚えられます。厚さは5~8mm程度(一円玉約3~5枚分の厚み)を保つと、強度と軽さのバランスが取れます。
この技法をマスターすれば、急須や土瓶だけでなく、茶碗や皿にも応用できます。
碁笥底が基本です。